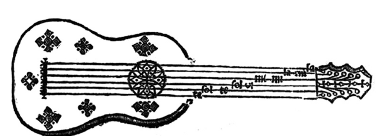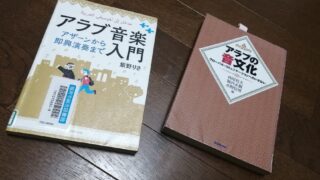アラブ音楽は、西洋音楽とかなり異なる音楽体系。それを知ると、当たり前と思っていた音楽体系だけが当たり前じゃなかった! という驚きを体験ができます。アラブ音楽の特徴をざっくりいうとこんな感じです。
・アラブ音楽は、マカーム(旋法)と呼ばれる多様な音階と旋律様式を中心に作られている。マカーム(旋法)の種類は、アラブ各地の多様なものの総数は100種を超える。例えばイラクなど現代の東アラブ諸地域では、主要なものは8種類で、そこからの派生形を入れて42種類。トルコやエジプトでは30種類前後。北アフリカのマグレブでは24種類など。西洋音階の長音階と短音階に比べると多様性が顕著。マカームは撥弦楽器ウードによる音の分析と深い関係がある。
・各マカームには、開始音、終始音、音階の幅、音の上昇下降の流れなどによるパターン認識があり、各マカームに特有の情緒感がある。各マカームに対応するリズム形式(イーカーウ)や歌唱内容があったり、マカームの組み合わせによる楽曲構成が生まれたり、器楽曲・器楽合奏・器楽と歌・詩の朗唱・器楽即興演奏・伝承歌謡メドレーなどを組み合わせた一時間ほどにも及ぶ組曲形式(ワスラ)が生まれたりと、マカームがアラブ音楽の中心概念になっている。またマカームのパターンに精通することで、器楽の即興演奏(タクスィーム)も可能になる。
・マカームに使用される音階は、一般に1/4音の微小音階まで表記されている。楽譜上には、♭マークに斜め線を交差させて、ハーフフラット(1/4音)を表現したりする。1/4音よりもっと詳細に分けて、全音を9コーマという単位に分割し、1オクターブ53コーマとする53平均律の音楽理論もある。西洋音階の12平均律と比べれば、その細かさは驚異的。
・アラブ音楽は単旋律で進行し、和声、コードの発想が希薄。単旋律でも微小音階を含む多様な旋法(マカーム)を駆使する方向で進化したので、非常に内容豊富な音楽となる。
・アラブ音楽のリズム型式はイーカーウと呼ばれ、その内容は総数で100種にも分類される。それらのリズムの違いが、各地域の音楽の個性に重要な役割を果たす。例えばイラクでは25種のイーカーウに分類され、2/4拍子などの単純な拍から、7/8拍子や36/4拍子などという複雑な拍子もある。これらのイーカーウは、西アジアでは片面太鼓リックの打法、アンダルシアではドラムのダルブッカとタンバリンのタッルの打法によってリズムが形作られる。
・アラブ音楽では詩の朗唱の重要度が高く、詩の韻律にはイーカーウの拍とは異なる独自の詳細な韻律規則がある。その詩の韻律とアラブ音楽のイーカーウの相互関係がアラブ音楽のリズム感の深みともなる。
・アラブ音楽は、長期に渡りイスラム教の地域と重なっていたため、コーランの朗唱、宗教的な詩の朗唱、イスラム神秘主義教団のセマー(旋舞)など、イスラム教との結びつきが強くなったのも確か。しかし、例えばシリアのアレッポなどでは、ユダヤ教徒、シリアカトリック教徒、シリア正教徒などでも、マカームの美意識は共有されてきたし、キリスト教の聖歌を内容とするマカームの歌もあった。また、宗教に関係のない恋の歌の伝統的な歌詞も多く、現代的なポップなアラブ歌謡や、ベリーダンスなどの舞踊のための音楽もある。宗教観と離れた形の人類的な音楽としてアラブ音楽をイメージすることができる。
ざっくりいうと、こんなところです。極めて詳細多様に表現性を広げながら、パターン化による使いやすさも実現しているという、複雑化と単純化のバランスが絶妙な音楽体系のように思われます。
以上の主要参考文献は「アラブの音文化 西尾哲夫ほか編」とウイキペディアなどあっちこっち。