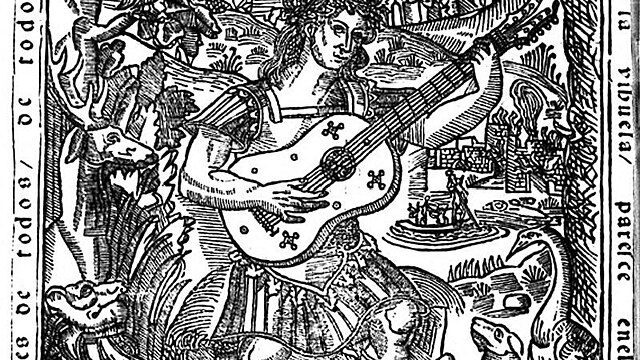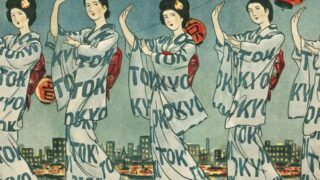前回の続きで、今回のテーマは戦後の盆踊りの変化について。
戦時中基本的に休止傾向だった盆踊りは、戦死者の追悼・暗い世相の払拭という願いのもと早期に再開されていきましたが、生活全般の急激な民主化と著しい経済発展という大変動の中で、盆踊りは大きく変容していきます。変容の中身は多岐に渡りますが、ざっくり箇条書きにすると、次のような点が挙げられます。(参考・盆踊りの戦後史 大石始著 ほか)
・進駐軍の方針により、戦時体制の基盤となっていた隣組や町内会が解体され、地縁組織の活動も禁止された。そしてこれらに替わるものとして新町内会が再編され、地域作りの中心になる公民館が整備された。その結果、地域の盆踊りは公民館主導に変化し、公民館の設置目的(社会教育法20条)である「住民の教養向上、健康増進、情操純化を図る」という目的に沿って、健全で民主的なレクリエーション活動という色付けに変化した(伝統色の後退)。
・NHKラジオ放送で始まった「のど自慢」をきっかけに民謡ブームが起こり、地方の民謡の全国的知名度が上がり、民謡や踊りの愛好会、サークル、研究会、保存会、民謡関連の連盟や協会が様々結成され、各団体主催の講習会や学校・公民館での振り付け指導などが広がった。こうして歌い方や踊り方が整理され、地域を超えた広がりの基盤ができていった。
・朝鮮戦争特需後の急速な経済復興により国内観光ブームが起きた。すると、各地の温泉街や観光の町が「〇〇温泉音頭」などを創作して観光資源として使用した。地方の盆踊りの中には、表面的には伝統の装いを取るものの、実は観光ブームを当て込んで創作されたものが少なくない。
・アメリカ流の「レクリエーション活動」の一環として世界の民俗音楽を踊る「フォークダンス」が一般化し、盆踊りもその一部に取り込まれ、多様な機会に盆踊りが踊られることが多くなった。さらにフォークダンスの発展形として日本発のダンス文化である「レクリエーション・ダンス」が生まれて、ポップスや流行歌にも振り付けをして踊ることが広がると、その何でもありの自由自在な感覚が盆踊りにも再接続され、例えばディスコ音楽で盆踊りを踊るような新感覚の盆踊り文化に繋がった。
・高度経済成長期に入ると地方から三大都市圏に大量の人口移動が起きた。中学卒業後に集団就職でやって来た労働者群と都市と農村の著しい収入格差から都市に集中するようになった会社員群などであり、これら「民族移動」とも称されるほどの人口移動の受け皿として、都市近郊に次々と団地やニュータウンや新興住宅地が建設された。こうして生まれた新コミュニティの人たちは、都市文化的なライフスタイルを主導する反面、故郷喪失者として故郷への郷愁を強く抱えていたため、手作り盆踊りの中に「ふるさと」イメージを再構築しようとした。こうして、「ふるさと盆踊り」「ふるさと祭り」などの名を冠した、ふるさとを意識した新興都市住民の盆踊りがあちこちに作られた。
・団地やニュータウンのような新コミュニティは、何の縁もない人たちが人為的に偶然集まる形で形成されており、このようなバラバラの人たちが地域社会を形成するためには盆踊りの創作は有益かつ必要であった。団地やニュータウンの主たる構成員は子育て中夫婦と子供による核家族であったが、この時代の父は地域よりも職場に所属してほとんど在宅しないので、勢い団地やニュータウンの祭りは母と子供たちが主役となった。具体的には子供会と婦人部が主体となって全体の計画が作られ、必然的に子供たちを主人公とする盆踊りが計画立案された。そして、子供が喜ぶ形のひとつとして、アニメソング音頭や子供向けの出し物中心の盆踊りが生まれていった。
・手塚治虫以降続々と新漫画が登場し、漫画文化・テレビアニメ文化が子供たちの心を捉えるようになると、そこにレコード産業も参入し、1970年以降アニメソング音頭が続々と作られた。テレビアニメの始めや終わりの部分で、子供も簡単に踊れる振り付けの紹介とともに、毎週繰り返しアニメソング音頭が放送された。上記のような団地やニュータウンの盆踊が子供中心に計画される中、全国どこの盆踊りでもアニメソング音頭が欠かせないものとなった。
・団地やニュータウンの盆踊りのような都市生活者のための盆踊りがある一方、工業地帯や企業城下町などの労働者の受け皿となる盆踊りとして、大工場や大企業主催の盆踊り大会のような企業サイドの盆踊大会、さらには共産党が主催する労働者サイドからの盆踊り大会なども多数生まれた。このような組織的な大規模盆踊り大会では、工場・企業と地域との絆が意識されることが多く、バンド演奏やダンスや各種催しが組み込まれ、最後の締めくくりを盆踊りとする地域大文化祭という様相のものが多かった。
・都市への人口移動によって上記のように様々な新盆踊りが生まれた背後で、農村部は盆踊りの担い手が減少し、地域で細々と続けられていた盆踊りがいつのまにか消滅していくものが増えた。
・以上のような新盆踊りの多様な創造の中、盆踊りは何でもありの風潮が強くなり、ドラえもん音頭、アラレちゃん音頭など、アニソン音頭の定番曲のほか、1970年代半ばころには、研ナオコの「京都の女の子」、1970年代後半には田中星児の「ビューティフルサンデー」、1980年代にはドイツのディスコ音楽の「バハマ・ママ」、1980年代後半から荻野目洋子の「ダンシングヒーロー」などが盆踊りの定番曲として広がり、ポップスやディスコ音楽も盆踊り曲として普通になった。振り付けはレクリエーションダンスからの影響も広く見られた。
・1990年代に入ると、チームのダンスパフォーマンスの優劣を競い合うダンスイベント型が生まれ、高知の「よさこい祭り」、北海道の「よさこいソーラン祭り」など、各地でよさこい系祭りがブームになった。その踊りと衣装はチーム毎に工夫が凝らされ、仲間との一体感と個人の主役感が感じられる点で、子供と先導の大人による閑散とした踊りの輪があまり元気なく動くような踊りと一線を画し、若者の情熱を捉えることに成功した。このようなダンスパフォーマンス型の踊りは、学校の運動会や地域のイベントにも広がり、その踊りの振り付けは、伝統的な盆踊りスタイルとは一線を画し、キビキビと大きく物語を含んで派手に見せる劇的なものになった。
・2011の東日本大震災以降、都市部において、野外フェスティバル風の盆踊大会が始まった。「プロジェクトFUKUSIMA!納涼!盆踊り」と「中野駅前大盆踊り大会」が2013年に始まり、どちらも土地の恒例イベントとして土地に繋がりながらも、土地の外から集まった人が踊ることを志向するという点が新しい動きであった。外から人が集まるためにSNS、インターネットの情報拡散力が力を持った。このフェス風の盆踊りは、コロナ禍以降更に盛り上がっていく(次回に書きたいと思っています)
・都市部において野外フェス風の盆踊り大会が産声を上げた一方、地方では高齢化で年々規模が縮小されていく中、クラウドファンディングによる再生の試みにより、各地の盆踊り愛好家が数多く参加して成功する例も出てきた(滋賀県高島市の高島おどり)。これもコミュニティ外の人を巻き込む盆踊りの流れという点で、上記の野外フェス風の盆踊り大会と同じく、SNS、インターネットの力が関与している。
第二次大戦後の盆踊りの変化は、ざっくり箇条書きでも、こんなに様々な動きがあり、その変化の大きさ驚かされます。次回、コロナ禍による中断後の変化について考えてみたいと思っています。
つづく