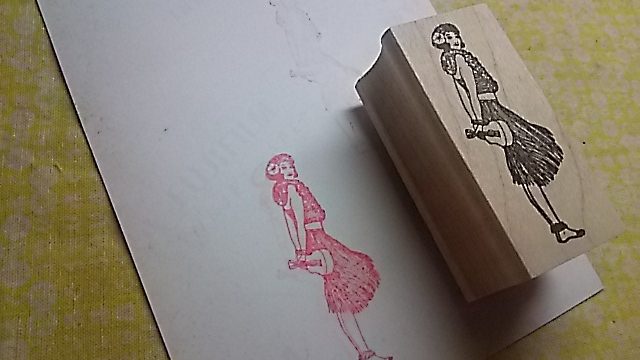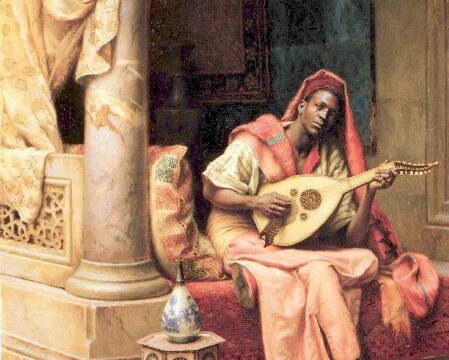2020年頃から起きたコロナ禍により、人が集まるイベントの多くが中止となる中、夏祭りや盆踊りの多くも自粛が決定されました。次善の策としてオンライン盆踊りの試みが多数実施され、じっくり踊り方を自室で練習できたり、チャットで語り合えたりという新たな面もあったものの、どこか満たされない空虚感が残ったのも偽らざるところでしょう。実際に人が身体を運んで集まることが盆踊りの必須要件なのだということが、コロナ禍によってクローズアップされたとも言えるでしょう。
コロナ禍が明けて各地で盆踊りが再開されると、盆踊りは従前にない新たな盛り上がりを見せはじめているようです。人が身体を持ち寄って集まれること、自由に移動してどこにでも行けること、空間を共有して一緒に体を動かせることなどの大切さが再認識されたのかもしれません。YouTube、インターネット、SNSの情報をもとに広域から人が集まり、熱を帯びて踊る老若男女の姿があちこちで見られます。第三次ジャポニズムとも言われる日本ブームと円安の中で世界中から観光客が来日するようになり、盆踊りの輪の中にあたりまえに外国人の姿が見られます。それらの外国人の多くは、アニメや漫画などの日本発コンテンツに子供のときから親しんでいるためか、盆踊りに異国情緒に止まらない郷愁を感じ、初体験なのに懐かしさを感じる人も少なくないのだとか。盆踊りは常に地域コミュニティのものとしてあったわけですが、地域コミュニティの外の人がどんどん入り込むことが加速して、盆踊りを生み出すコミュニティの流動化と拡大という新フェーズに入っているようにも思えます。
ではコロナ明け後の盆踊りの状況について、都市と地方の例を見てみたいと思います。
・東京大阪など大都市部では、フェス風にイベント化された盆踊りが盛り上がりを見せています。「中野駅前大盆踊り大会」「歌舞伎町BON ODORI」「渋谷盆踊りSHIBUYA BONODORI」「道頓堀盆踊インターナショナル」など様々なものがあります。その公約数的な特徴を挙げると、老若男女国籍を問わず誰でも参加できるダンスイベントとして企画されていること、日本の民謡からポップスやダンスミュージックなど和洋の幅広い音楽をミックスしていること、若者から外国人まで幅広い人が盛り上がって踊っておりディスコやフェスのノリを再現していること、フェスのようなコール&レスポンスの盛り上がり、DJによる進行、生演奏への回帰も見られること、その場で覚えられるプロの振り付けと指導、外国人の参加を意識していること、一休さんなどアニソンも流れるが低年齢の子供向けではなく若者から大人向けの選曲になっていること、特に十代の若者による情報の拡散、若い女性がゆかた姿を人に見せられる場になるなど若い男女が集まりたくなる雰囲気、子供から老人まで幅広い年齢層が性別も国籍も関係なく参加していること、地縁や血縁や団地縁などコミュニティの縁で集まっていた従来の様子とは異なり、SNSの情報などで一夜に集まった縁で繋がった人たち(SNS縁?)が中心の盆踊りであること、中央に櫓が組まれるなど輪を描いて回るという盆踊の基本の仕組みは維持されていること、2018年にボン・ジョヴィのヒット曲「Livin on a prayer」で踊ることがはじまったが、コロナ明け後一層の流行を見せ、ボン・ジョヴィ本人もこれに反応するなど国際的な話題性もあること、などです。
https://youtu.be/cF1ToXI1AjI?si=x_mjMxX7IEuvVrvg
・「東京五輪音頭2020」「8000人による大阪万博の大屋根リング盆踊り」など、国をあげての公的な催しでは、世界に向けて発信する日本的コンテンツとして盆踊りが結構強く押し出されています。予めYouTubeなどで踊り方の解説動画が出て、それを学んだ上で参加するなど、インターネットの活用が見られます。
・コロナ明け後、都市型の盆踊りでは内容に次のようないくつかの変化があるのではとの指摘がされています。踊りの指導者として場を取り仕切っていた高齢者の引退による世代交代、高齢者引退に伴い細かい所作をそろえるなど細部へのこだわりが消滅し、細かいことにこだわらない自由な感覚が表面化、腰を振るとか最後に決めポーズをとるなどダンスのような所作の増加、この音が聞こえたらこうするというようなイレギュラー要素の導入、地域の振り付けを受け継ぐ意思が希薄化し年々変わっていくことを許容する傾向、単純な曲を長く踊ることによるトランス的な心地よさが消滅し、短い曲に変化を入れながら踊るという短時間内の盛り上がりを重視する傾向、長い曲では飽きてしまうので短い曲を選曲する傾向、など。参考→ https://note.com/66yune99/n/n736f31661cef
・地方では、高齢化が進む半面、定住人口(そこに居住している人)、交流人口(観光や仕事などで一時的に訪れている人)、関係人口(居住はしていないが継続的に関係を持つ人)の三種の人口それぞれに新しい人口の流入が見られ、盆踊りの盛り上がりの担い手が生まれつつあります。たとえば、定住人口としては都会生活に飽き足らなくなった若い世代の地方移住者の姿がありますし、交流人口としては地方への旅や地方の祭りを求める祭り愛好家や外国人の姿が見られますし、関係人口としては普段は都市で仕事をしながら週末には農村に何度も訪れて地域起こしを手伝うことに生きがいを見出す人々などの姿が目立つようになっています。定住人口、交流人口、関係人口のどの場面でも、SNS、インターネット、YouTubeによる情報収集と交流が基礎的なインフラになっています。これらの新たな人口流入が、地方の盆踊りの消滅を阻止し、新たな活気の源泉となりつつあるようです。
以上のように、都市においても地方においても、SNSなどを基本インフラとして、コミュニティの外からの人の流入を受け入れることによって、盆踊りが新たな活気を帯び始めています。従来の盆踊りがコミュニティの内側の結びつきを強めるという閉鎖系の働きをしてきたのに対し、最近の盆踊がコミュニティの垣根を取り払い内外を繋げる開放性の働きに移行しつつあるとすれば、数百年の歴史の盆踊りが歴史的転換点を迎えているようにも思えます。