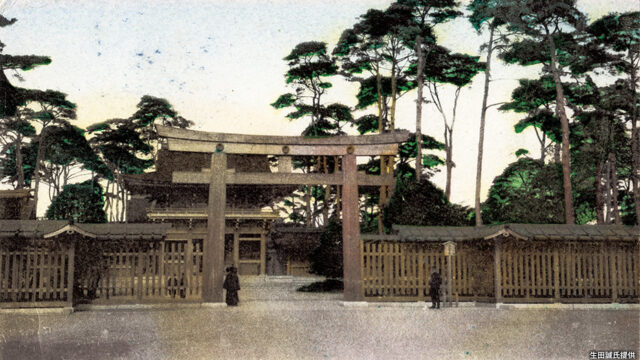前回の続き、第一の中断後に生じた盆踊の変化が今回のテーマ
明治初期から長らく禁止されていた盆踊りは、近代化が一段落した明治末から大正にかけて各地で徐々に再開されますが、中断期間が長かったことや、悪しき習俗という禁止理由を払拭する必用があったことや、急速な近代化による社会の変化に対応する必用などの理由から、おおむね次のような変質が起こりました。
① 健全化 土地の若い男女の性の開放交流の場としての盆踊りは消滅方向。徹夜踊りをやめて、日をまたがない時間までに終了することが基本になり、朝まで半トランスで踊り続けるようなエネルギーの発露も消滅方向。下ネタ混じりの自由な歌のやりとりも減少し、健全な正調の盆踊歌が作られた。
② 大衆化・観光化・定型化・芸能化 上のように健全な盆踊り歌が作られたことで、盆踊りから即興性が消えていった。振り付けも踊りやすいものが新しく作られて定型化し、外部の人も容易に真似て学ぶことができるようになり、盆踊りが郷土外への広がりを持ち大衆化しはじめた。盆踊りの観光資源化が起き、盆踊りは土地の人が踊るものから観客が見て楽しむ芸能という側面も生まれてきた。
③ レコード、ラジオの普及と東京音頭の創作 大正時代から昭和初期にかけてレコードとラジオという新メディアが普及してくる中で、1933年に東京音頭が創作されてレコードとラジオに乗って日本中で大ブームを巻き起こした。東京音頭の原曲「丸の内音頭」は、1932年に丸の内から有楽町あたりの飲食店が地域振興イベントとして発案し、西條八十作曲・中山晋平作詞でビクターが製作し、白木屋が浴衣をデザイン販売し、日本舞踊の中の新舞踊運動を代表する初代花柳寿美が振り付けを考案し、赤坂の芸者も集めて日比谷公園大盆踊大会を開催して大盛況。これを受けて翌年東京音頭と改称し全国プロモーションを展開し、日本各地を席巻する空前の大ヒットとなった。以後日本各地で同様のイベント盆踊りが開かれるようになり、盆踊り共演大会(コンテスト)も盛んになり、凝った衣装と徹底的に練習したダンスパフォーマンスの競争、観客と審査員受けを狙って派手な振り付けなど、現代のよさこい系祭りのような競い合い盆踊りの流れが生まれた。このブームの裏側では東京の一部地域で細々と歌われ踊られていた昔ながらの盆踊が消えていった。このように東京音頭によって、後の創作盆踊の原型が生まれ、盆踊りは創作するもの、生歌と生演奏がなくてもよくなり音源で踊るもの、町起こしなどの目的をもって計画的に開催するもの(イベント化)、人の目を引くために競うもの、という現代に繋がる新しい盆踊り像が生まれた。
参考 盆踊りの戦後史 大石始 ほか
つづく 次回は第二の中断後、戦後盆踊りの変化について