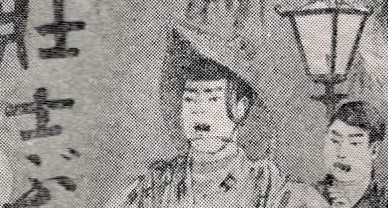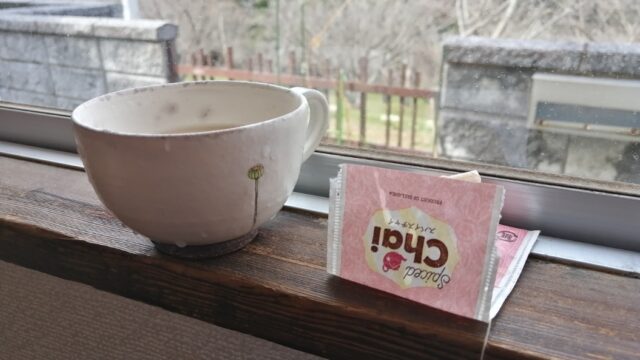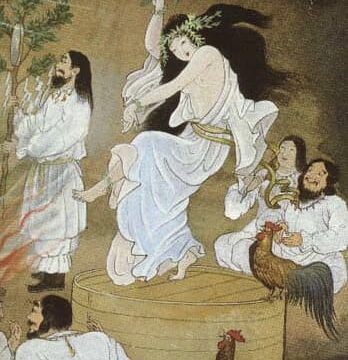演歌と名のつく歌が生まれたのは明治時代。現代の演歌とは大分おもむきが異なり、政治的な主張を歌で行うものでした。明治政府が自由民権運動を抑え込もうとする中、街角の演説がだめなら歌でどうだということで、「演説⇒演歌」となったわけです。当時自由民権運動の活動家のことを「壮士」と言ったため、そのような歌は壮士演歌とか壮士節などと呼ばれました。壮士演歌を歌う様子は、編み笠をあみだにかぶり、腰には白いへこおびを巻き付け、太いステッキを振り上げて、歌はまるでどなりつけるようという調子だったそうです。五七調にのせて「悲憤慷慨アジアの前途を観察すれば 文運日々に進みゆき 武運盛んな日本も 治外法権撤去せず 税権回復まだならず 跋扈無礼の赤ひげめ …」などと、数人の若者が入れ代わり立ち代わり延々と熱く歌っていると、通りかかる人は足を止めて大変な人だかりになったそうです。このように演歌とは、政治性、社会性を帯びて人々に訴えかけるものだったのですが、その中から歌として洗練されてくるものが生まれ、明治から大正にかけて歌の内容のバリエーションも広がって、社会主義的主張になったり、戦争賞賛的になったり、耽美的になったり、宣伝的娯楽的になったり、世相切り取りゴシップ的になったりと、様々な流行歌が生まれていくことになります。
街角で怒鳴りつけるように壮士が歌うという形のものは、さすがに録音や動画を見つけることができませんでしたが、演歌を歌として洗練させ明治から大正にかけて活躍した作詞作曲歌(シンガーソングライター)添田唖蝉坊の再現動画(土取利行氏による再現)はたくさん見られます。次の動画は添田唖然坊作詞作曲の明治40年の「増税節」。合いの手に入る「トツアッセー」「マシタカゼイゼイ」という声は、ただの掛け声と思わせて、実は「咄、圧政」「増したか税税」の意味がこめられているそうで、なかなかしゃれています。
次は同じく添田唖蝉坊の「のんき節」。大正時代の作品です。批判精神を滑稽味にくるんだ中に深みがあり、現代の感覚で聞いても違和感がありません。おもしろがりながら客観的に世相を見ることができるように聴く人を誘導する手腕は大したもの。自分も真似して歌詞を作ってみたくなる感じもします。そんなところが流行歌のひとつの秘訣でしょうか。
流行り唄五十年 添田知道著