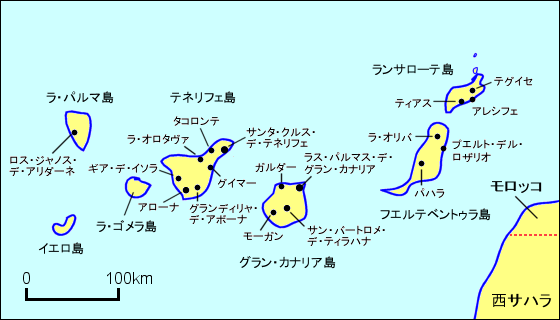イエズス会の宣教師ルイス・フロイスは、「ヨーロッパ文化と日本文化」の著作の中で、こう書いています。
「われわれはオルガンに合わせて歌う時の協和音と調和を重んずる。日本人はそれをかしましいと考え、一向に楽しまない」
「われわれはクラヴォ、ヴィオラ、フルート、ドセイン(葦笛)等のメロディによって愉快になる。日本人にとっては、われわれのすべての楽器は、不愉快と嫌悪を感じる」
逆に、日本の当時の音楽が西洋人にどう聞こえるについては、ルイス・フロイスはこう書いています。
「われわれの間の種々の音響の音楽は音色がよく快感を与える。日本のは単調な響きでやかましく鳴りひびき、ただ戦慄を与えるばかりである」
つまり互いに理解できず不快に感じたわけです。
不快に感じるものを聞かされた時、「だから相手の文化は遅れている」という反応を起こしがちですが、相手の音楽を解釈するソフトが聞く人の中に形成されていないというだけのことで、文化的優劣の問題ではないでしょう。
相互に解釈ソフトが形成されてない中で特筆すべきは、昨日も書きましたが、秀吉の反応の鋭敏さだと思うのです。
秀吉は、帰国した遣欧使節団の少年たちが演奏する(クラヴォ、アルパ、ラウデ、ラヴェキーニャ)音楽を非常に注意深く、かつ 珍しそうに聞き、同じ楽器で三度、演奏し歌うことを命じ、そして楽器を一つずつ自らの手にとって、少年たちにいろいろと質問し、さらに他のヴィオラ・デ・アルコとレアレージョ(携帯風琴)を演奏するように命じ、それらのすべてをきわめて珍しそうに観察し、彼らに種々話しかけ、「汝らが、日本人であることを大変うれしく思う」 と述べたというルイス・フロイスの記述です。
秀吉は、聞きなれない音楽に対して不快や嫌悪という方向ではなく、興味、関心、知識という方向の反応をしています。三度も演奏を繰り返させ、楽器のひとつひとつを手に取り、細かく質問をしたのは、この西洋音楽というソフトを理解し吸収しようとしていたのではないでしょうか。日本に急接近してくる西洋各国が音楽というソフトを利用して日本で何をしようとしているのか、宣教師がこんなに音楽を重視している理由は何か、西洋音楽が持つ機能と効果は何か、日本にとって危険な要素と日本が利用できることは何か…など秀吉の頭脳は猛スピード回転していたように思えます。
このように考えると、秀吉の少年たちに向けて発した最後の言葉、「汝らが、日本人であることを大変うれしく思う」という言葉が、ある種の重みをもって聞こえてきます。「宣教師たちが何年もかけて少年たちに西洋音楽を仕込んでくれた。これは使えるソフトを手に入れたぞ。汝らが日本人で本当によかった」こんなふうにも聞こえます。
火縄銃が種子島が来ると、あれよあれよと自分のものにしてしまった戦国大名たちのように、秀吉は西洋音楽というソフトも自家薬籠中の物として世界戦略に臨もうとしていたのかもしれません。
秀吉はこの翌年から朝鮮出兵を開始します。朝鮮の次には中国や東南アジアも含めて勢力圏を作り、西洋各国に対抗する戦略だったという説もあるようです。音楽を通してキリスト教を民衆に浸透させようとしていた宣教師たちと、その音楽を吸収して逆利用する可能性を見ていた秀吉と、そんな歴史ドラマが垣間見えます。