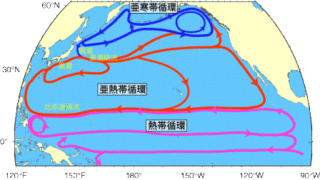楽器(ギター等)、造作、家具、伝統建築などに多用されてきたシトカスプルースは、近年著しく供給不足で、価格高騰中。入手がだんだん難しくなってきています。
シトカスプルースは自然林から高齢樹大径木が伐採され、切ったあと簡単には再生しないので、無計画に伐採すればやがて枯渇してしまいます。そのため、カナダやアラスカではシトカスプルースの伐採、販売、貿易に関する規制を強化しており、大量輸入国の中国、日本、台湾では、少ない流通からの取り合いの様相。また代替材(ルッツスプルースなど)を探す動きも加速しているとか。
シトカスプルースの大径木☟

20世紀以降の材木使用の黒歴史を言えば、「取り尽くしたら次を探せ」という言葉に集約されるかもしれません。人気の材種を競って取って十数年で絶滅枯渇すると次の材を探してきて、それも競って取ってまた枯渇、その代替材を探してまた枯渇…ということをずっと繰り返しているようです。この持続不可能な循環は地球の資源のあらゆる面に向けられているので、自然全体と人間自身の絶滅枯渇に向けて爆速進行中の様相。宇宙人目線で見れば、人間ってばかだなあ、と思うことでしょう。
この持続不可能な循環を止めるには、ひとつの材種に群がるのをやめる、たとえば「ギターの表はやっぱりスプルースかシダーでしょ」とか、「裏板はローズウッドでなくちゃ。ローズウッドの中でもブラジルのハカランダが最高」、「ウクレレはコアでなくちゃ。それもこんな木目でなくちゃ」などの発想から転換して、「いろんな木にはいろんな響きや趣きがあってそれぞれが面白いよね」という方向、つまり「最高の追求」から「多様性を楽しむ」、「みんなのあこがれに向けて競う」から「自分が愉しいかどうか」に発想をシフトしていく必要があるのだろうと思います。最高という発想はたったひとつに収れんしていくので、どうしてもそれに群がるというパターンが生まれますが、多様性は無数に向かって開かれていくので、何にも群れずに多方向に拡散していきます。意識も行動も逆向きで、おそらくこの逆向きが、絶滅危惧種人間が引き返すために残された唯一にして無数の道のように思えます。
というわけで、最近、今まで使ったことのない色んな材種を使ったウクレレ、一本ごとの多様な響きを楽しむウクレレ、あまり無理することなく入手できる木を使ったウクレレ、という方向性で作ってみようと思っているしだいです。