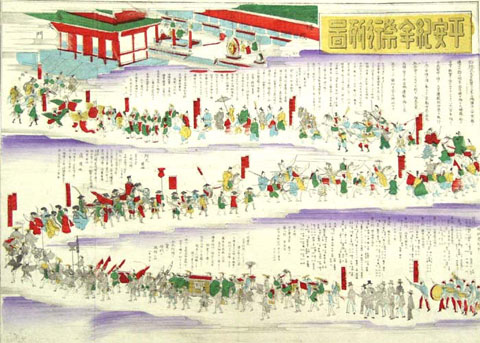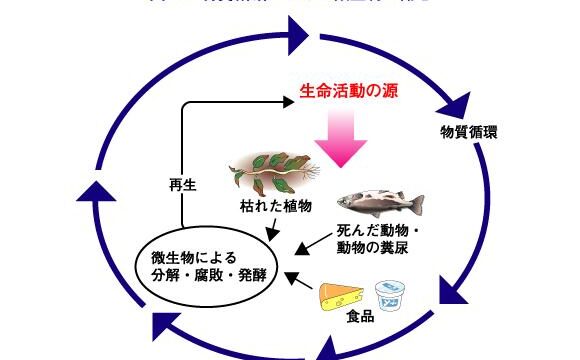能舞台の奥の壁(鏡板)には一本の松が描かれています。これは庭にある神の依り代の松が鏡に映っていることを表現しているのだそうです。つまり、能・狂言は、この松に降臨する神に向けて、神への捧げものとして執り行われるものなのだとか。
能はもちろん人が見るものとしての面はありますが、能楽家の意識は今なおまっすぐ神に向けられていて、能楽師囃子方高安流大鼓方の佃良太郎氏も、「実際、自分のことを音楽家だと思ったことはありませんし、お客様に対して見せている意識もほとんどありません。すべては神様に向けてのものという意識なので…」と、次のページで言われています。→ https://www.jiyu.ac.jp/jgs100/tsukuda.html
また狂言師の茂山千三郎さんは、神社で奉納中に記憶がないままに奉納が終了した経験を語られているのですが、もしかしたら、松に降臨した神は、ただお客様として見物なさるだけでなく、演者とひとつになって舞ったり演じたりされるのかもしれません。↓
次の動画を見ると、能楽が「祈りの芸術」であることがよくわかるので、おすすめです。能楽を通した 日本の美・心 映像本編↓
能「翁」