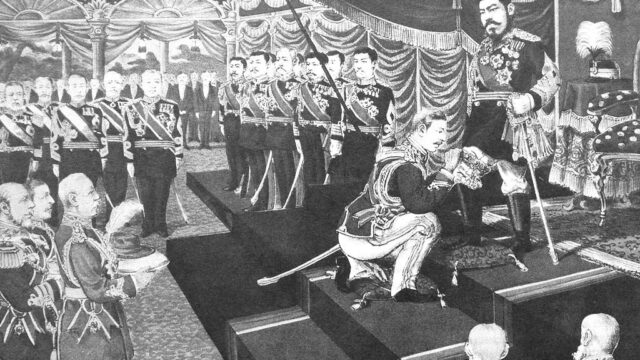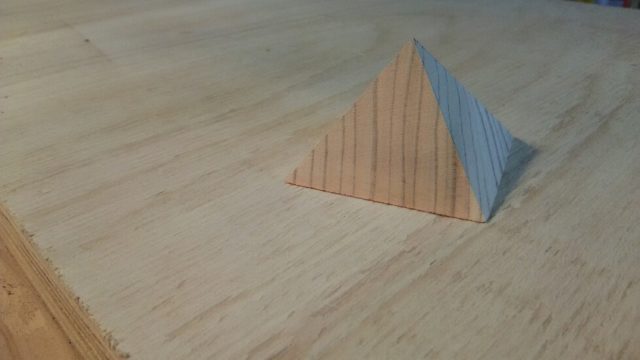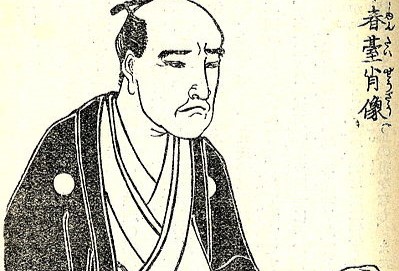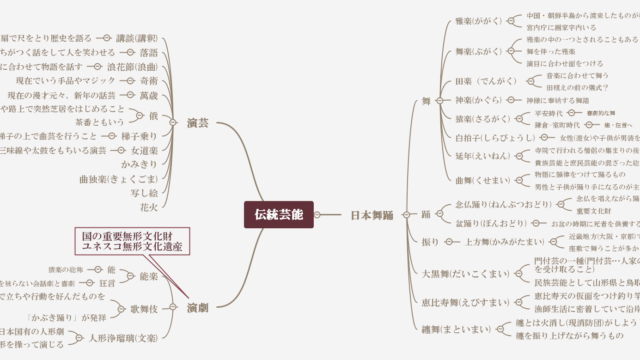昭和30年~50年頃に小中高教育を受けた人の多くが体験したフォークダンス。マイムマイム、オクラホマミキサー、コロブチカなどが定番です。運動会で踊ったり、週一回昼休みに踊る時間があったりして、男女が公然と手をつなぐワクワク感と、気になる子がだんだん近づいてくるドキドキなどが、シニア世代の思い出の1ページです。残念ながら平成にはもうほとんど消滅してしまったようです。
戦後日本のフォークダンスのはじまりは、1946年12月に長崎でウィンフィールド・ニブロ氏によるスクエアダンスの指導が最初で、翌年からスクエアダンス全国指導者講習会が開催されると、戦時中歌うことも笑うことも男女が手をつなぐことも禁じられていた人々に、新鮮な開放の喜びをもって迎えられ、日本中で大流行しました。
これは、「人生を楽しく創造的に」というアメリカのレクリエーション運動の理念の一環です。サイクリング、ユースホステル運動、ハイキング、キャンピング、フォークダンスなどの諸活動が、日本の民主化というアメリカの占領政策を背景に紹介され、その一部が学校教育にも取り入れられたのです。占領政策下の啓蒙活動という面はありますが、強制的な文脈は特に見られず、戦後の希望を探していた日本人の心に肯定的に響いて、昭和の日本に明るいエネルギーをもたらしました。
戦前は日本の女性には選挙権がなく、戦後1945年にようやく女性にも選挙権が認められ、1946年の第22回総選挙で39名の女性議員が誕生しました。フォークダンスが始まるのもまさに同じ年です。男女が公然と同じ立場で手をつなぎ、共に踊り、最初は気恥ずかったけれどもやってみれば思いのほか楽しく、ワクワクしてドキドキして前向きな気持ちになり、上の動画のように女性のパワーに男性がリードされがちだけど、それも案外悪くなかった…そんな体験と並行して女性参政権が始まるというのは、もしかしたら非常によく考えぬかれた占領政策だったのかもなあとも思います。仮に占領政策であったとしても、フォークダンスを含むレクリエーション運動は、全体として日本の歴史に明るい光をもたらしたように思います。