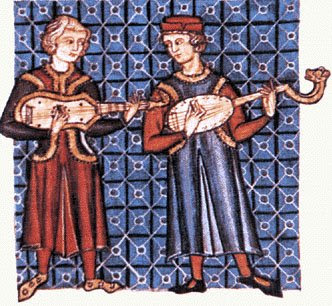伝統邦楽の世界では、音程を感じにくい音である「噪音(非楽音)」が結構愛されている、という話の続きですが、わかりやすい例としては、例えば尺八や篠笛。尺八は普通に吹くだけでも風が吹くような噪音が混ざりますが、ムラ息という技法で強いかすれ音を強調するとさらに味わいが深まり、様々な景色が脳裏をよぎります。次の動画の6分過ぎあたりで紹介している技法です。↓
それから横笛の能管のヒシギという技法。鋭く切り裂くような高音に神がかったような感じが出ます。↓
箏では「すり爪」や「散らし爪」などの爪と糸のこすれる音による技法。「打ち爪」という弦を叩く技法や「添え爪」というビリつく音の技法もあります。↓
次は三味線のサワリ☟
声の分野では喉をしめる独特の発声法が長唄など様々な分野で普通に見られます。
能楽の世阿弥は、「花鏡」の中で、老人の声には若い人の艶っぽい「生音」がなくなって、さびのある枯淡の「残声」があるから、老人の謡は声で有利だという趣旨のことを書いており、これは西洋的な「楽音」と正反対の考えと言えます。
このように、伝統的な邦楽には、西洋音楽が美しくない音として排除してきた噪音(非楽音)があふれています。美しくないどころか、そこに深い味わいがあるという邦楽の感性は、一体どこから来ているのでしょうか。
前に下のリンクのように書いたのですが、自然音の中には100kHzを超える超高周波があふれ、邦楽の楽器にも100kHzを超える超高周波が多く含まれているということにヒントがありそうです(これに対して現代の西洋音楽の楽器は、人の可聴域の限界である20kHzまでの音しか含まれていないという)。つまり西洋音楽は自然の周波数を雑音としてカットする方向に進化し、邦楽は自然の周波数を音楽の核心として残したということのように思われます。この違いには、西洋が、この世を罪の国、天を神の国と二分する発想で、この世の音を雑音として排除して混ざり気のない天の音楽を追求しようとしたのに対し、日本は、自然の中に八百万の神々が宿るという発想で自然の音そのものを求めたという思想の違いが反映されているのかもしれません。↓
なお、可聴域を超える周波数を人は感知できないはずだと思われるかもしれませんが、体表面で感知しているという研究があります。その研究によれば、可聴音と超高周波を同時に聴くとき脳深部の神経活動を劇的に活性化し快適性が増加することが観測できるそうです。↓
参考文献 日本音楽がわかる本 千葉優子著