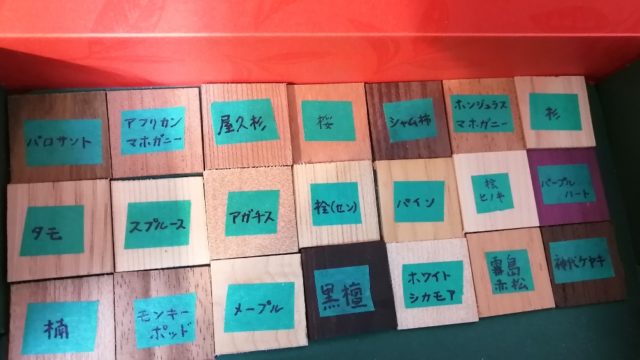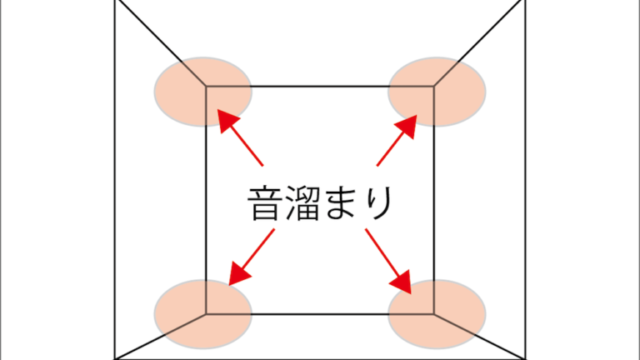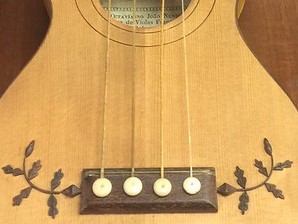平安時代末期の抜群におもしろい天皇に後白河天皇(1127-1192、天皇退位後は上皇、出家後は法皇、以下天皇の呼び方でまとめさせていただきます)がいます。何がおもしろいかというと、当時の庶民の間で流行した歌謡曲「今様(いまよう)」に若いころからはまってしまって、周囲から今様狂いとばかにされながらも、当時の白拍子(しらびょうし)、傀儡女(くぐつめ)、遊女(あそびめ)など、最下層の女性を先生に迎えて、数々の今様の歌をコレクションし、今様の歌い方を真剣に習い覚え、今様の歌い方を後世に伝えるために今様のすべてをまとめた「梁塵秘抄(りょうじんひしょう)」全二十巻を書きあげたのです(1180年頃)。現在そのごく一部しか残っていないのですが、様々な今様を体系的に整理して歌詞を残したうえ、その歌い方を詳細に解説し尽くしたすごい全集であったようです。
丁度昨日の朝、NHK朝ドラの「らんまん」が最終回を迎え、植物に情熱を傾けた牧野万太郎が生涯かけてまとめた日本植物図鑑が完成したという回だったのですが、今様に生涯をかけた後白河天皇と梁塵秘抄のエピソードと重なるところがあるように感じました。
またNHKといえば日曜夜のドラマ「鎌倉殿の13人」でも西田敏行演じる後白河天皇が乱世をかき乱す人物として描かれたようですが、後白河天皇という人は真逆とも言える描き方が成立する人のようで、そこがまたこの人のおもしろさです。
この後白河天皇は即位前の名は雅仁親王と言いますが、元々天皇になる予定は全くなく、気楽に遊び暮らし、今様狂いとして周囲の評価はきわめて低く、誰にも期待されていない人でした。鳥羽上皇は後白河天皇のことを「天皇の器量にあらず」と断言し、崇徳上皇は「文にも武にもあらず、能もなく芸もなし」と言い放ち、雅仁親王の側近である信西(藤原通憲)ですら「和漢の間、比類少きの暗主」というひどい言いよう。
ところがそんな雅人親王が様々なタイミングもあって天皇になってしまいました。臨時の中継ぎ登板のような即位であったのですが、運命は後白河天皇を放っておいてはくれず、天皇退位後も上皇として長年にわたり政治をつかさどることとなります。平清盛、源頼朝、源義経、木曽義仲など大変なメンバーの中に身を置き続けて、繰り返される乱の中、幽閉脱出の危機もありました。平家から源氏へと権力が移動する激動の中で、常に台風の目となって舵取りをした手腕は大したものだという評価と、武家を翻弄してかき乱しただけの今様狂いという評価の両方があって、いまだ評価が定まりきらない人のようです。私としては、900年の時がたちながら評価を定められないというだけでも、どんなものさしでも測りきれない、よほどスケールの大きな人物だったのではないのかと思うしだい。少なくとも、梁塵秘抄をあらわして古代の庶民感覚を目の前に残してくれただけでも十分に偉業だと思います。
後白河天皇が残した梁塵秘抄を読めば、900年前のちまたの教育のない庶民が親しんだ歌が、それも傀儡女や遊女など春を売ることをなりわいとするような最下層民が歌った歌が、かくも深淵で美しく、かつ親しみ深いことに驚かされます。ぎりぎりの困窮の中で人生を見つめざるを得ないからこそ生まれる繊細な感性と哲学的な思考があるように思います。
梁塵秘抄は歌詞の巻が十巻、歌い方の理論実践&エピソード編とも言うべき口伝の巻が十巻の合計二十巻になる万葉集にも匹敵するほどの大著でした。現在残っているのは歌詞の方が巻第一の一部と巻第二の全部のみで、それでも566首もの歌詞が残っています。口伝の方は、巻第一の一部と巻第十が発見されています。今後まだ見つかっていないものが出てきたら大発見です。このように散逸したものが多いのですが、それでも平安時代末期の庶民歌謡566首を味わうことができるのはすごいことです。
それらの歌は文字として残っているために、現代では文学の範疇で捉えられることが多いのですが、後白河天皇はあくまでも声に出す歌として残したかったということは意識しておく必要があります。それはあくまでも歌謡でした。それも現代歌謡のようにプロが歌うのを聞くというより、自ら口ずさんで歌うための音楽だったということで、だからこそ歌い方の口伝が十巻も書かれているわけです。
では、後白河天皇が集めた566首の中から今日は有名なものを三つほど紹介します。
「遊びをせんとや生れけむ 戯れせんとや生れけん 遊ぶ子供の声きけば 我が身さえこそ動(ゆる)がるれ」
(訳・遊ぶために生まれて来たのだろうか。戯れるために生まれて来たのだろうか。遊んでいる子供の声を聴いていると、私の身体も自然に動いてしまう。)
「舞え舞え蝸牛 舞はぬものならば 馬の子や牛の子に蹴させてん 踏破せてん 真に美しく舞うたらば 華の園まで遊ばせん」
(訳・舞え舞え、かたつむり。舞わないなら、馬の子や牛の子に蹴らせよう。踏み破らせよう。真に美しく舞ったなら、花の園で遊ばせよう)
「仏は常にいませども 現(うつつ)ならぬぞあわれなる 人の音せぬ暁に ほのかに夢に見え給ふ」
(訳・仏はいつもいらっしゃるが、姿が見えないのが尊い。人が寝静まった暁に、ほのかに夢に現れてくださる)