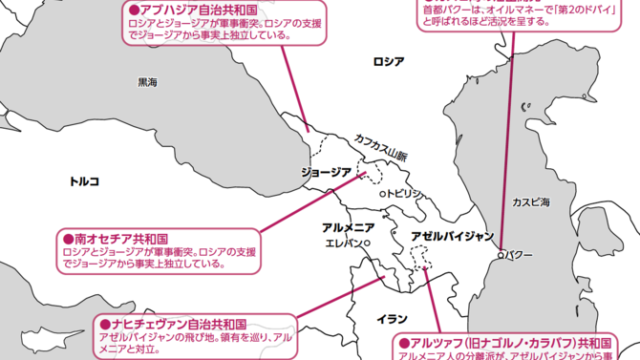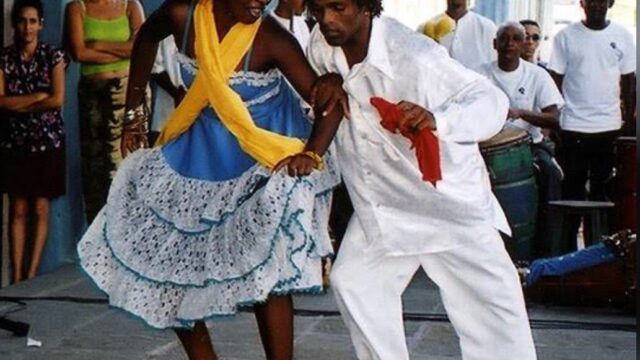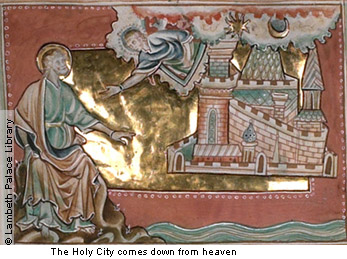先日書いた https://ittosya.net/homo-neanderthalensis の続きですが、現生人類であるホモ・サピエンスのような虚構を作るという認知革命が起きなかったネアンデルタール人は、果たして音楽を持っていたのでしょうか。
認知革命の結果、神話やシンボルなどの架空の物語を通して見知らぬ人々と結び付くことができるようになったホモ・サピエンスに対して、ネアンデルタール人は直接見知った人としか協力することができなかったと言われています。宗教・政治・民族・世代・身分・性別などの様々な物語(虚構)を背景にする音楽の多くは、ネアンデルタール人は創ることも理解することもできなかったのかもしれません。
しかしだからと言ってネアンデルタール人は音楽を持たなかったというのは乱暴な話のように思えます。ネアンデルタール人も言語と感情を持っていた以上、感情が乗った言葉の抑揚やリズムの変化はきっとあったはずで、それは自然に歌になったかもしれません。また見知った人の間で協力関係を持って社会を作っていたのですから、共に声やリズムを合わせることで、結び付きを強化することが起きても不思議ではありません。周囲を取り囲む自然の音に耳を傾けることで身を守り狩猟採集の生活をしていた以上、音に対する感性は現代人以上に鋭敏だったはずで、自然の音や気配の微妙な変化の読み取ってその模倣をすることが音楽の発生を促すのは自然なことのように思えます。
このように考えると、言葉・感情・生活・社会・自然という要素から、音楽はおのずと生まれそうに思えます。そんな虚構以前の基礎的な音楽がホモ・サピエンスでもネアンデルタール人でも変わりなく存在するのではないでしょうか。その虚構以前の基礎的な音楽の上に様々な虚構が乗っているのがホモ・サピエンスである現代人の音楽事情かもしれません。
参考 サピエンス全史 ユヴァール・ノア・ハラリ著
冒頭の写真はホモ・サピエンスであるクロマニョン人の家族の復元