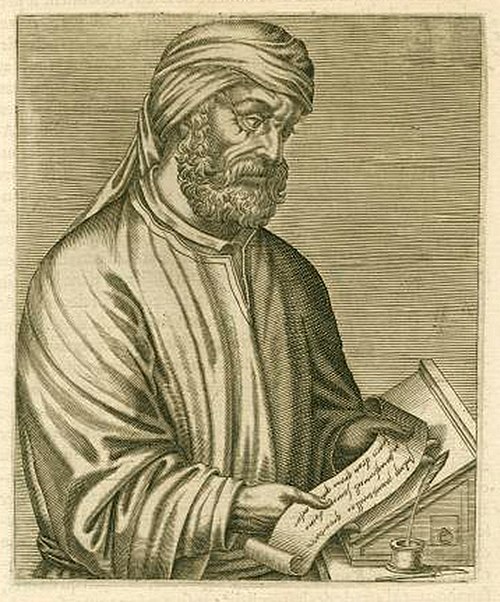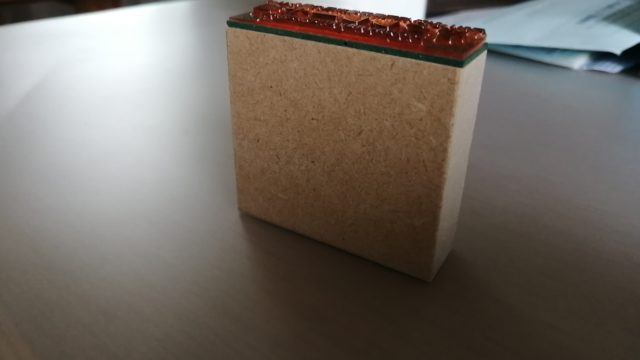ハーメルンの笛吹き男のような放浪楽師が市民たちから悪魔的な存在とみなされていたことを前々回に書きましたが、そのような悪魔楽師観はキリスト教初期にすでに存在していました。
たとえば、2世紀カルタゴのキリスト教神学者テルトゥリアヌス(冒頭の絵の人)の音楽観。その概要は、「音楽は、暴飲暴食、性的快楽、ねたみやそねみなどのあらゆる種類の悪徳へと人間を誘惑するために、不適切なやり方で用いられる。民衆がこの罪深い喜びを味わうと、楽師と芸人の仲介で悪魔となじみになり、神から遠く引き離される。真のキリスト教徒は、悪魔の友なる楽師を、邪心崇拝へと後戻りを意味する彼らの催しと同様に忌避すべきである」というものでした。
3世紀の神学者クレーメンス・フォン・アレクサンドリアは、フルートやプサルテリウムの演奏、舞踊や合唱隊の登場といった許しがたい行為は、少なくとも宗教的な祝祭日には許容できないと述べました。
4世紀のローマカトリック教会の教父ヒエロニムスは、若い娘たちはフルート、ハープ、リラなどいかなる楽器であろうと耳にしてはならないと命じました。
4世紀から5世紀の教父アウグスティヌスは、芸人や楽師たちに報酬を支払うことは大いなる罪である、なぜなら不道徳的かつ瀆神的な演奏と引き換えに悪魔に報酬を支払うことにならからだ、として芸人や楽師たちに報酬を支払ってはならないという命令を発しました。また彼は娼婦と楽師が聖体拝領に加わることも拒否しようとしました。
このようにキリスト教初期の指導者たちの多くが、芸人とその音楽を悪魔又は悪魔の仲介と見て、その音楽を聞くことも報酬を支払うことも罪であると考えていました。この思想が一般民衆社会にも強く浸透し、ハーメルンの笛吹き男の事件を起きた13世紀ドイツにも続いていたわけです。
「悪魔」「罪」という概念を軸に楽師を差別する考え方は日本人には馴染みが薄いですが、しかしひるがえって見れば、日本では「ツミ」「ケガレ」という概念を軸に芸人を賎民として差別してきました。いずれにしも、「悪魔」「罪」とか、「ツミ」「ケガレ」などのワードを軸に芸人やその音楽を悪者にするのは、神の都合というより人の都合だったんじゃないのか?、という気がしなくもありません。
参考 中世ヨーロッパ放浪芸人の文化史 マルギット・バッハフィッシャー著
ウイキペディア ほか