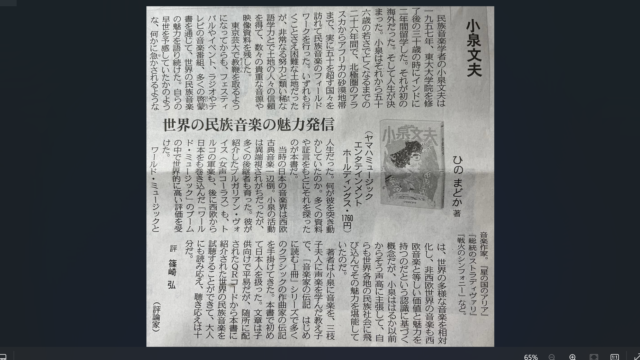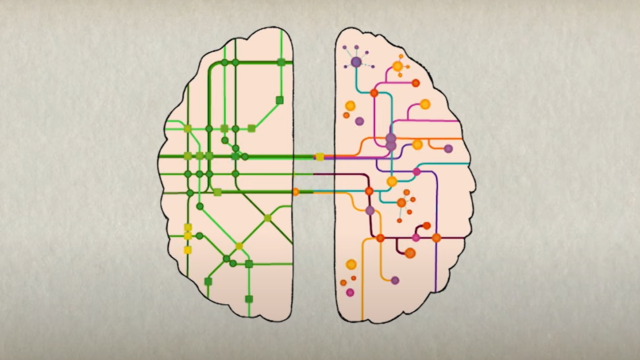外国から木を輸入して、それまで使っていた日本の木の代替材として利用するときに、新榧とか米ヒバとか南洋桂とか、日本の木の名前を付けてしまう(全く別種の木でもお構いなしに)という名付け方について先日書きましたが、このやり方の問題なところは、輸入前の土地でその木が形成していた生態系や周辺文化のことが、すっかり忘却されてしまうことにあるように思います。
たとえば、「新榧」と名付けられたシトカスプルースは、北米アラスカやカナダ西海岸に分布し、氷河に囲まれたフィヨルドとトウヒやツガの苔むした巨木の原生林の生態系や、ザトウクジラなども生きる海の生態系や、先住民トリンギット族の暮らしや文化など、様々な生命現象と結びついていたわけですが、「新榧」と名付けられたとたん、それらの原風景はすっかり消えてしまって、安価に大量に出回る「代替材」という個性のないどこか無機質なものに姿を変えてしまいます。下の写真のようなシトカスプルースの原風景が、みんな見えなくなってしまいます。



「新桂」や「南洋桂」や「南洋桧」などと、いろいろな名を付けられたアガチスも同じです。アガチスは、東南アジアからニュージーランド、フィジーなどオセアニア一帯に分布する常緑針葉樹で、それをニューギニアではアガチスと呼び、インドネシアではダマール、フィリピンではアルマシガ、マラヤではダマルミニャク、ニュージーランドではカウリと呼び、それぞれの土地の生態系と暮らしや文化と結び付いていたはずです。例えば、ニュージーランドのマオリ族は、この木をカヌーや建築材として活用しながら自然と共存して来ましたし、この木の樹脂は琥珀のような輝きを持つことから工藝や装飾品に利用されました。中には樹齢1000年を超えるものもあり、マオリ語で「森の神」を意味する「タネ・マフタ」と呼ばれる樹齢2000年の巨木(冒頭の写真の木)も存在しています。それらの原風景が、新桂、南洋桂、南洋桧などの名前からは、見えなくなってしまいます。
また、楽器業界では、マホガニー属ではないカヤ属の木をアフリカから輸入して、アフリカンマホガニーと呼び、従来のマホガニー属の木の代替材としているのが一般ですが、アフリカではその土地ならではの名前があるはずで、樹皮から薬をとったり、カヌーを作ったりと、原地の暮らしと結び付いるのですから、元の土地の名前を尊重した方が、ずっと深い背景を感じながら、楽器を楽しめるのではないでしょうか。
雑草という名の草はないとよく言いますが、木にも「代替材」という名の木はないと感じます。代替材として適当な名付けが始まると、それはとたんに個性も生命もない物体となり、いくらでも替えがあるし、いくら伐り取っていいという、そんな無機質な収奪の対象になってしまうように思えます。すっかり感覚がマヒして、背景で多様な生態系や現地の暮らしの循環が断ち切られていることが意識できなくなります。
この名前を勝手に変えるというやり方は、相手を支配する魔法か麻薬のようなところがあって、千と千尋の神隠しの話の中で、湯ばあばが相手の名前を奪って千やハクを支配したやり方と似ているような気がします。千とハクは元の名前を思い出すことで、その支配から抜け出していくわけですが、樹木の場合も、元の名前をわれわれが思い出して、その周辺に形成されていた生態系や文化に意識を届かせることで、正常な循環に立ち戻るはじめの一歩とすることができるのではないでしょうか。