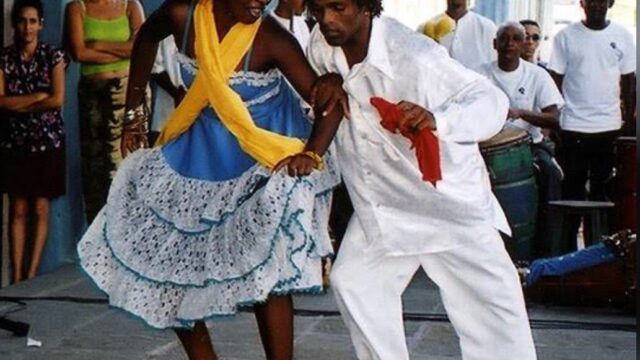いろんな日本の木でウクレレを作ってみたい私としては、そもそも日本の人はどんな木を暮らしの中で使いながら生きてきたのだろうということに興味がわきまして、弥生時代の遺跡の木製出土品に注目してみました。
鳥取県内の複数の遺跡から、古代山陰地方の弥生時代初期から古墳時代までの建物や木器の遺物が大量に発見されており、どのような木が生活に使われていたかが、細かくわかっています。特に青谷上寺地遺跡は良質な遺物が大量に発見保存されており、弥生の地下博物館と言われるほどです。
この古代山陰地方の遺跡では、河口付近などの湿潤な地域には掘立柱式高床建物(穀倉、神殿、豪族の館など権威性や公共性がある重要な建物と推測される)があり、周辺の小高い丘陵部分には庶民の住居である竪穴式住居があったようです。
まず掘立式高床建物の部材(青谷上寺地遺跡から発見された主要建築部材は81点のほとんどは掘立柱式高床建物の部材と考えられる)を樹種鑑定すると、針葉樹材が69%、広葉樹材が31%で、針葉樹材の内訳は、スギが最も多く36点、次いでヒノキ7点、イヌマキ、カヤ、モミがそれぞれ2、3点ずつ。広葉樹材の内訳は、多い順にヤブツバキ6点、ヤマグワ4点、クリ3点、サカキ2点、スダジイ2点、以下クスノキ、ヤブニッケイ、クヌギ類、ホオノキ、エノキが各1点。全体の傾向としては、スギ材の選択性が非常に高く、建物のあらゆる部分に使われていて、これは高床式建物の権威性や稲作の重要性を象徴する神聖な材木としてスギが選択されていた可能性が指摘されています。木目の緻密さから巨木スギが使用されていたことがわかり、出雲大社の巨大な柱もスギであったことなども考えると、山陰地方の稲作文明と巨木文化の結びつきが推測されるということです(ちなみにこの地方では海岸近くまで直径1メートルを超すスギの巨木が豊富に分布していたことが分かってます)。また、スギは鉄器を使わなくても、まだ広く使われていた石器で割り裂く方法で板を作ることが可能だったこともスギの選択性に影響していたと考えられます。柱材には、ヤブツバキ、サカキ、ヤマグワ、クリなど堅牢な広葉樹材が選択されています。
次に庶民の竪穴式住居の建築部材について見ると、いくつかの遺跡で内容は異なりますが、出てくる樹種を列挙すると、スギ、ヤマグワ、カシ類、ケヤキ、スダジイ、タブノキ、ツブラジイ、シデ類、クスノキ、クヌギ類、ヤブツバキ、クリ、ヤマザクラ、ネムノキ、ミツバウツギ、アカメガシワ、コナラ類、モクレン科と、極めて多様。スダジイが中心に使われている遺跡、クリが中心に使われている遺跡、多様な広葉樹が使われている遺跡など、遺跡ごとに個性がありますが、全体として見ると、弥生時代にはスダジイが選択的集中的に使われていたのが、時代が進むに連れてスダジイからクリへと選択性に変化が現れ、その後さらにいろいろな広葉樹材へと樹種選択性が多様化しています。庶民の竪穴式住居では生活周辺の森林(里山)の広葉樹が広く使われていて、スギが集中的に選択されていた掘立式高床建物とは異なる傾向です。
続いて建築部材以外の木器類(桶、蓋、楯、鋤、鍬、丸木舟、匙、武具、箱、田下駄、祭祀具など様々)を見ると、70%が針葉樹、30%が広葉樹という割合で、針葉樹の内80%がスギとなっていて、ここでもスギへの志向が顕著です。スギは丸木舟、桶、容器、田下駄、箱物、武具などあらゆるものに使われています。スギ以外の針葉樹としては、ヒノキが多く、ついでカヤ、モミ、イヌガヤ、イヌマキなどが少しずつ。次に広葉樹についてみると、用途に応じて使いわけられており、漆塗りの高坏にケヤキ、透かし彫り入りの精巧な容器にヤマグワ、農具や道具の柄には強靭なカシ類、サカキ、ヤブツバキ、臼や容器にはトチノキ、突き具の柄にはタブノキか使われています。面白いのは、建築部材として多用されていたスダジイやクリが、木器には全く使われていないということで、樹木特性に応じた使い分けがされていたことがうかがえます。
以上が山陰地方の遺跡における樹木の利用傾向ですが、他の地方の遺跡のことも少し触れますと、静岡市の登呂遺跡や山木遺跡という太平洋側の遺跡でもスギの選択が多いことが確認されます。また、時代をさかのぼって縄文時代の遺跡になりますと、青森市の三内丸山遺跡で、巨大なクリ丸太の柱の痕が発見されています。縄文早期から前期にかけての福井県の鳥浜貝塚では、建築材としてクリ、ヤナギ、ハンノキ、ナナカマド、アカメガシワ、カエデ類、トネリコ、ヤチダモが使用され、石斧の柄にユズリハ、サカキ、ヤブツバキ、弓や武具にカシ類、トネリコ、クリ、容器にトチノキが使用されていて、地方と時代に応じて、使われる樹種に変化が見られます。
以上をまとめると、古代山陰地方では、巨木の針葉樹(スギ、ヒノキなど)の森が近くにあり、特にスギを大切なものと考える巨木文明があったこと、そのため重要な建物や神聖な物はスギで作ることを好んだこと、庶民の生活周辺には非常に多様な広葉樹林の里山があり、庶民はこの広葉樹をふんだんに使い分けて生活していたことなどがわかります。針葉樹と広葉樹の両方の樹種が生活周辺にふんだんにあって使い分けができた文明というのは、実はとても珍しいことで、たとえばヨーロッパのドイツの森などは、主な樹種は広葉樹ではナラ、ブナ、針葉樹ではトウヒ、マツの4樹種だけというのと比べると、信じられないほどの豊かさでと言えます。日本の文明の区別として、弥生式土器文明、縄文式土器文明、狩猟文明、稲作文明などの区分が意識にのぼることが多いですが、マクロでみると、日本は一貫して森林文明であったということはもっと強調されていいかもしれません。そうすると、戦後の日本人の生活が森林から離れ、針葉樹の拡大植林で森林が激変し、人為的に改変されたまま使われることもなく放置され荒れ果てた森林が広がっている現状は、実は日本の文明の最も深い危機であるようにも思われてきます。花粉症や近時の熊出没被害などもその森林の危機からの警告とも言えるでしょう。
私が日本の木を使ってウクレレを作りたいと思うのは、古代人がバランスよく様々な木を使って森林の健全な更新と循環に役立ってきた暮らしのように、森の循環を取り戻す暮らしを探る試みでもあります。
参考
「広葉樹資源の管理と活用 第6章 古代山陰地方の木器文化」 海青社
「森林の崩壊」 白井裕子
「森林で日本は蘇る 白井裕子」 ほか