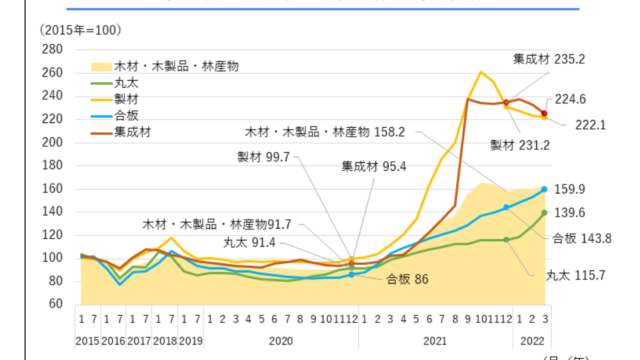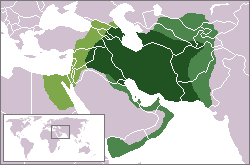前回書いたように、日本に三拍子が入ってきた経緯は、三拍子が皆無に近かった江戸時代、西洋の三拍子が紹介され始めた明治時代、日本人作の三拍子曲が急増してくる大正時代、古賀メロディに代表される三拍子の大衆歌謡が流行する昭和世代という流れでした。
こうして昭和までに三拍子が日本人にすっかり浸透したように見えますが、日本人の手拍子を見ていると、どこか二拍子的あるいは四拍子的な感じが漂うことがないでしょうか。
例えば、<1・2・3 / 2・2・3 / 3・2・3 / 4・2・3>(太字は強拍)という三拍子の曲があるとして、全部の数字で手を叩けば三拍子のリズムがはっきりと出ますが、太字のところだけで手を叩き、細字の2・3のところでは、手揉み、手すり、手こねと言ったふうの動きで間を取るという、そんな動きが見られることがあります(若い世代にはあまり見られませんが高齢世代にありがち)。
こうすると太字の1234が強く意識されるので、あたかも二拍子か四拍子のような感覚も生まれてきます。。細字の二拍目三拍目は、音の揺れ・こぶし・メリスマ(1音節に多くの音符があてられる装飾的な旋律法)のような雰囲気になって、「拍」というよりも伸縮自在な「間(ま)」という感覚に近づきます。
あくまで仮説ですが、日本人はこうして拍を伸縮自在な間に捉え直しながら、古くからある二拍子又は四拍子の感覚の中に三拍子の感覚を混ぜ込むという技法を使っているような気がします。こうすると、二拍子も三拍子も四拍子もいっしょくたに同じ流儀で音楽を楽しむことができます。様々なジャンルのコンサートでは日本の聴衆からよく手拍子が湧いてきたりしますが、あれはリズムに乗っているというよりも、リズムを日本的な間の感性に引き込んでいるのかもしれません。
また、三拍子のゆっくりした曲(例えば「家路」「仰げば尊し」など)を昭和世代の人がアカペラで歌ったりハーモニカを吹いたりしているのを聞くと、もうひとつ別の四拍子化現象も見られます。歌詞を伸ばす部分を一拍分長くしたり、小節の間に一拍分の息継ぎを入れたりして、自然に間延びさせて四拍子化してしまうのです。原曲を改変してしまう間違いを犯しているのですが、本人は何とも気持ちよさそうに、何のリズムにもとらわれず伸び伸びとやったりします。
日本人はすごいですね。世界のどんな音楽もとりこんでしまう特殊技術です。三拍子を理解していないと言えばそのとおりですが、異文化を「間」という余白の部分で吸収してしまうのは日本人の才能でしょうか。
ところで拍手しながら手を揉んだり手をすったり方法の起源ですが、どうやら民謡などにあるようです。次の博多祝い歌では、拍手しながら手をするというのが正しい所作とされているのだとか。
それから次の民謡の手拍子の解説。手をふる、手をする、手をもむ、手をこねるという動きの練習が解説されていて、福島県では手こね、島根県では手すりと言うなどと、呼び方の説明もあります。