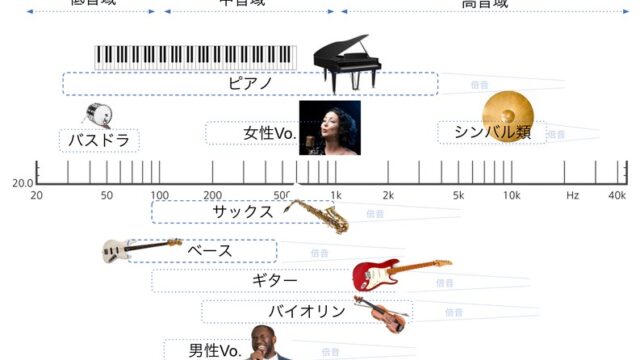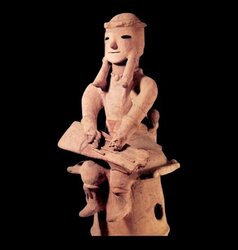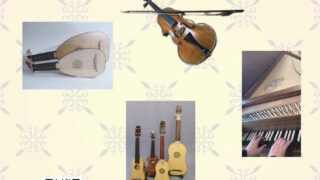1932年大改訂による第二期『満洲唱歌集』には、次の1940年大改訂までの間に、以下のような戦争を扱う曲目が入ってきています。
第五学年 (1935)《軍旗へ》(1931年12月の古賀中佐の戦死)
第五学年 (1935)《ああ百七十六騎》 (1905年の新開河の永沼中佐の挺身隊)
第六学年 (1936改訂1929初版) 《白襷隊》(1904 年11月の旅順戦の中村少尉)
第六学年 (1936改訂1929初版) 《北大営の戦》(1931年9月の柳条湖事件)
第六学年 (1936改訂1929初版) 《南嶺戦》(1931年9月の南嶺戦の倉本大佐)
第六学年 (1936改訂1929初版) 《嗚呼二烈士》(1905年、奉天戦の間諜の死)
第六学年 (1936改訂1929初版) 《殉国の女性》(1932年、陶家屯事件の川添巡査夫人
この頃の教科書編集委員は満州の現職教員が担っていたのですが、満州の教員自身が時局の変化を察知して、自発的に戦時色を教科書に盛り込んでいったのでしょうか。あるいは軍関係からそのような示唆又は指示があったのでしょうか。
いずれにしても、一般に教科書は歴史考証が終わった一般性のあることがらを内容とするものなので、直近の戦闘を取り上げて教科書化するというのは、あまり普通のことではありません。「満州事変とその後の満州国成立の正当性を子供たちに浸透させ、満州防衛の戦争準備をさせる」という特殊な目的を教科書が帯びてきて、教科書の変質が始まっているように思えます。
ところで上記の戦闘に関する満州唱歌の歌詞をあちこち検索したのですが、めぼしいものが見つけられませんでした。
市販本やネット上で紹介される満州唱歌は平和で懐かしい感じの曲目が中心で、戦時色の強いものは省略されがちなようです。しかしそのような戦争推進的な音楽からも目をそらすことなく検証することが、満州唱歌の歴史性・政治性・芸術性の全体像を知るために大切なことのように思えます。音楽の歴史は平和の歴史にも戦争の歴史にもなり得ることを忘れないために。